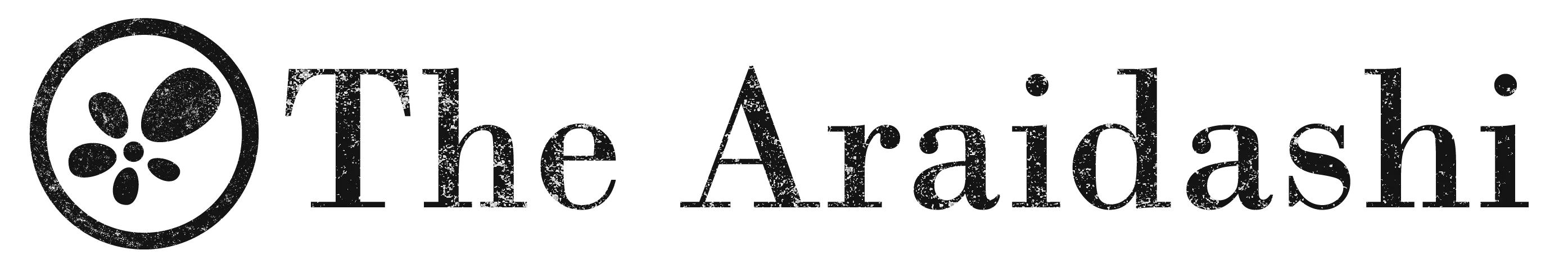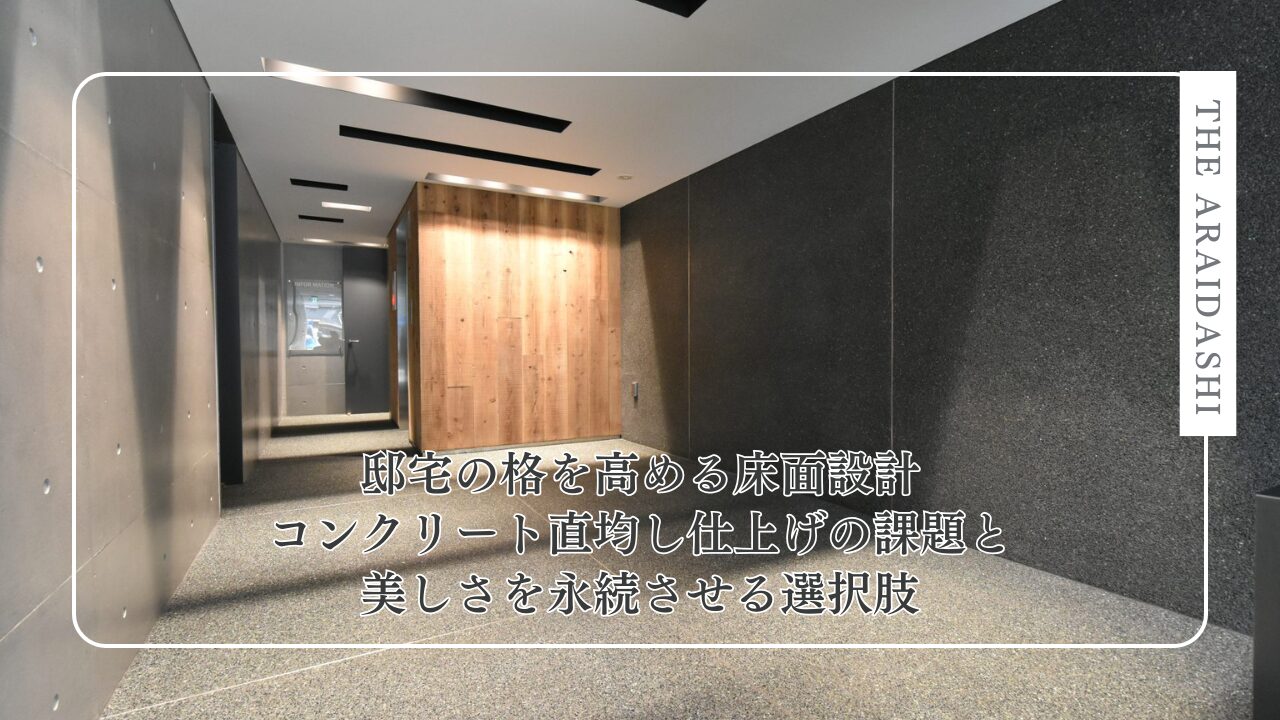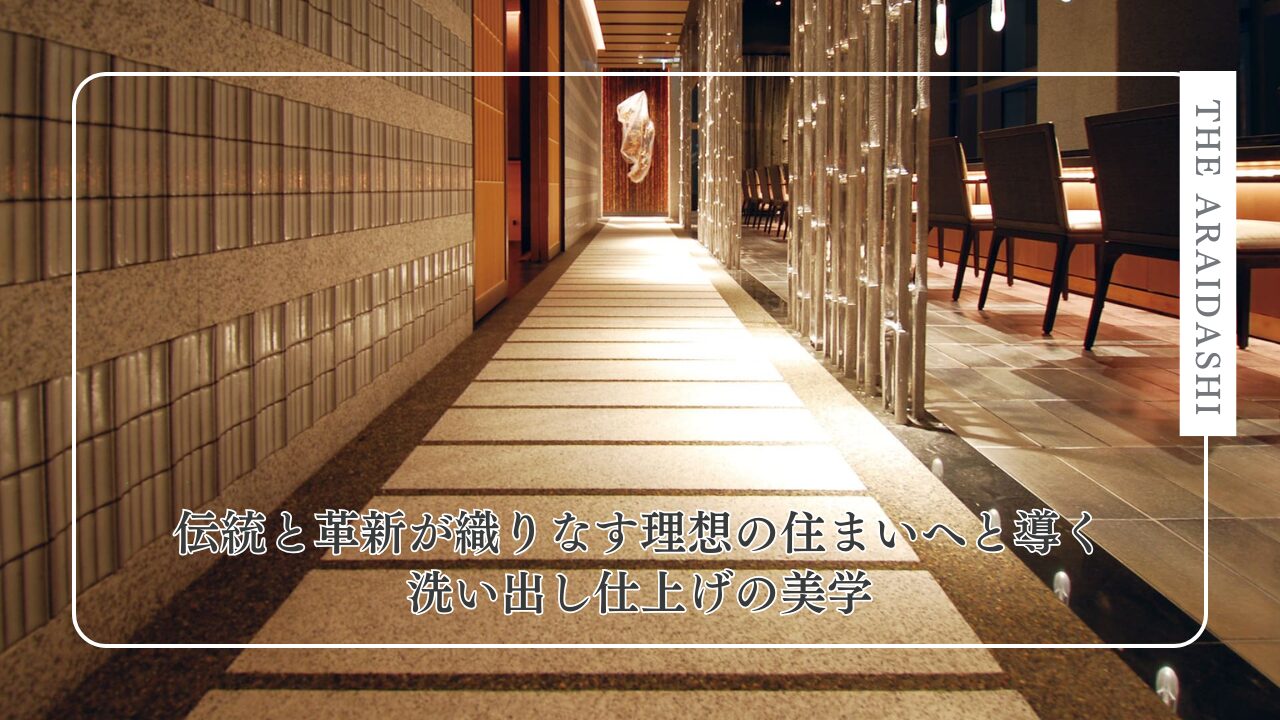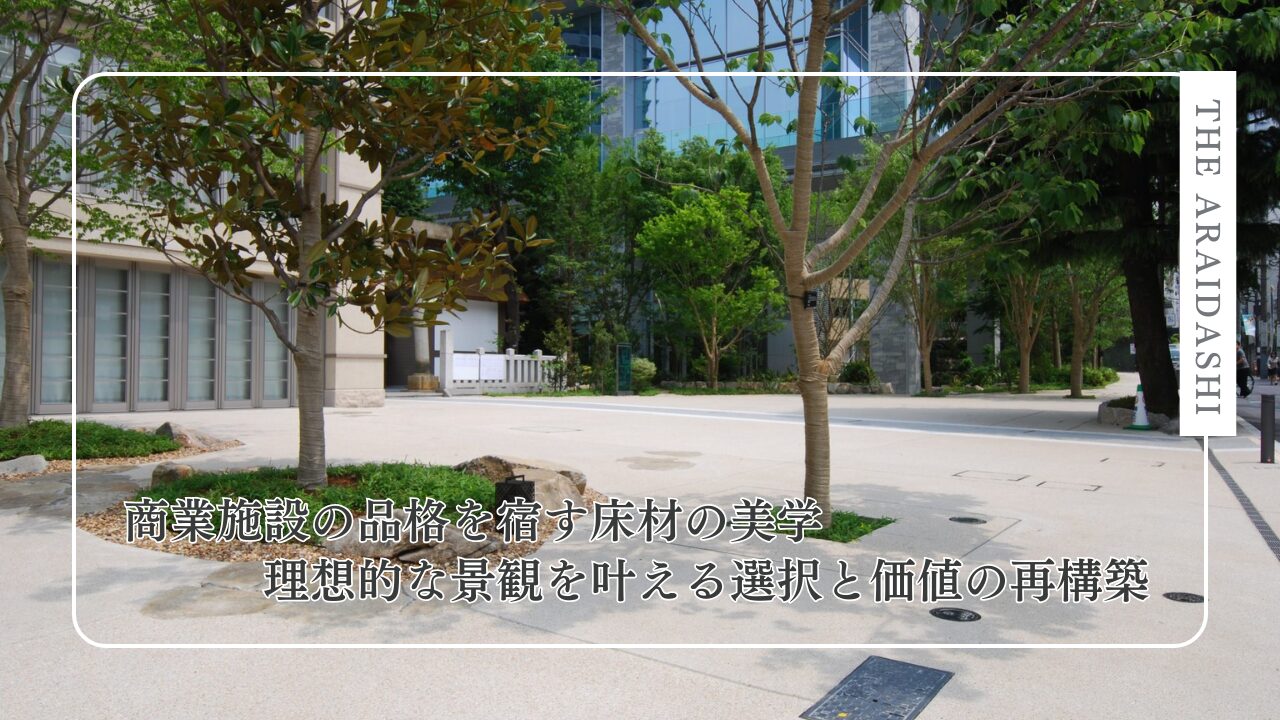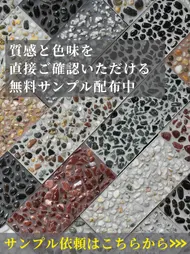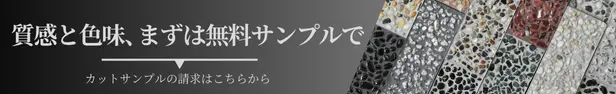【技術コラム】洗い出し舗装における収縮目地の設置間隔について
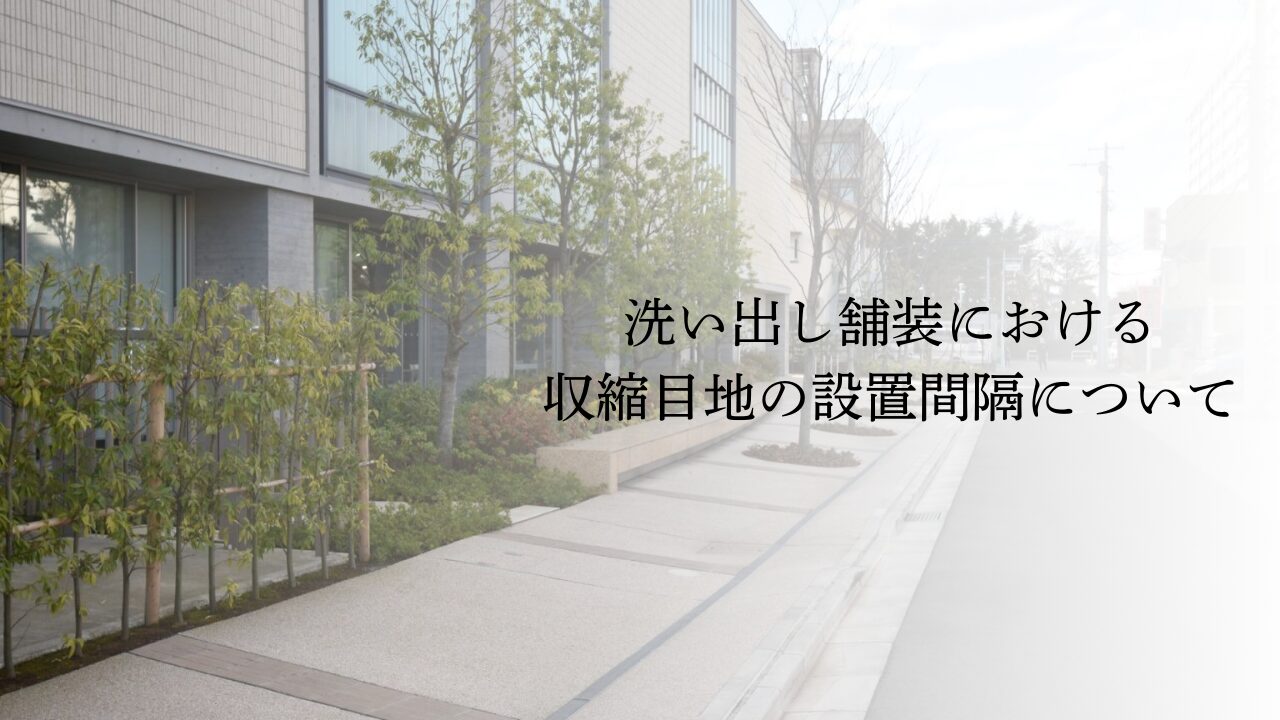
洗い出し舗装を設計・施工する際、意外と見落とされがちなのが「収縮目地」の設置です。
美観を重視するあまり目地を最小限にしたくなるところですが、目地設置の考え方を誤ると、仕上げ後にひび割れが発生してしまう可能性もあります。
今回は、洗い出し仕上げにおける収縮目地の設置間隔とその考え方について、実務経験や標準的な指針に基づいてご紹介します。
基本の考え方:下地コンクリートの目地に合わせる

まず前提として、洗い出し仕上げは下地コンクリートと一体化して動く仕上げ材です。そのため、基本的には以下のルールが原則です。
下地に収縮目地がある場合は、洗い出し面にも同じ位置で目地を設ける。
コンクリートの乾燥や温度変化による動きに仕上げが追従できないと、表層にひび割れが入るリスクがあります。
したがって、下地の収縮目地は、仕上げ層でもそのまま反映させることが鉄則です。
下地コンクリートに目地がない場合:3m以内を目安に
一方、まれに下地コンクリートに収縮目地が設けられていないケースもあります。
このような場合でも、洗い出しの仕上げ層には独自に目地を設ける必要があります。推奨される設置間隔は以下の通りです。
収縮目地の設置間隔:3m以内(できれば1.5〜2.0mが望ましい)
10mm〜20mm厚程度のセメント系仕上げ層は、乾燥収縮によってひび割れを生じやすいため、広すぎる区画はNGです。
できるだけ長辺:短辺の比率を抑え、正方形またはやや短辺寄りの形状で区画するのが理想的です。
目地の幅と仕上げの仕様

目地の幅については、下地のコンクリートに合わせて設定するのが基本です。
- 目地幅の目安:15mm~20mm程度
- 中には10mm幅で設計されるケースもあります
- 目地にはシーリング材を充填して仕上げるのが一般的
また、特別なデザイン性が求められる現場では、ステンレスや真鍮の見切り材(目地材)を使用する事例もあり、意匠的なアクセントとして機能させることも可能です。
洗い出し仕上げでよくある誤解と注意点
洗い出しは表面を石で覆っているため、「多少のクラックは目立たないから大丈夫」と思われがちですが、表面が割れると石が脱落したり、美観が損なわれる原因にもなります。
特に外構や公共空間では、耐久性と仕上げの美しさが長く保たれるよう、計画的な目地設計がとても重要です。
まとめ:洗い出しの収縮目地は“下地とセット”で考える
| 状況 | 推奨目地間隔 | コメント |
| 下地に収縮目地がある場合 | 同位置に設置 | 基本ルール |
| 下地に収縮目地がない場合 | 3m以内(理想は1.5〜2m) | 独自に設置が必要 |
| 目地幅 | 15〜20mm(10mmも可) | シーリングまたは金属目地材を使用 |
洗い出し舗装を美しく、かつ長持ちさせるためには、下地から仕上げまで一貫した目地設計が欠かせません。
設計段階で適切な目地設置を計画することで、施工後のトラブル防止にもつながります。
設計・施工に関するご相談がありましたら、お気軽にヤブ原産業までお問い合わせください!

コンクリート洗い出しのメリット・デメリットについてはこちらの記事がおすすめです。